都立中高一貫校の適性検査に出てくる問題文は、
冗長に展開されることが多く、
意図を理解して情報を整理しながら
読み進めるのはとても面倒ですよね。
今回は都立中の先生方が、
なぜそのような問題を作成するかを考えてみました。
まず、都立中の出題方針を確認すると
いくつかの共通点が見えてきます。
例えば
- 文章を読み取り、、、
- 身近な事象の中から課題を発見し、、、
- 文章の内容を的確に読み取ったり、、、
- 資料から情報を読み取り、、、
- 文章を読み、読み取った内容を、、、
- 数理的に分析し課題を見出す力、、、
など、課題を解決する前に、
現状を正しく認識する力が
求められていることがわかります。
これは、課題解決プロセスである
- 現状把握
- 理想形の設定
- ギャップを埋める対策
の1番目にあるもので、個人的には3つの中で
もっとも重要なプロセスだと考えています。
この能力を判断するために、
適性検査の問題文をやたら冗長にしてみたり
不要な情報を混ぜ込んだりしていると思われます。
現状を認識するということは、
今の状態を知るだけでなく、
そこに至った前提条件やルールも理解する必要があります。
長女の受験直前期、気分転換として
適性検査の黙読対決をしたときには
恥ずかしながら負けることの方が多かったです。
都立中受験生に求められる読解力は
かなりのレベルだと思います。
読解力を鍛える方法として
教科書や小説などを読むことも有効だと思いますが
適性検査の読みにくい冗長さに似ているのは
電化製品の説明書や利用規約、
他には行政の文章なども近いイメージです。
電化製品を買った時には説明書を読まずに、
まず電源を入れて触ってみるタイプの私には
厳しすぎます。orz
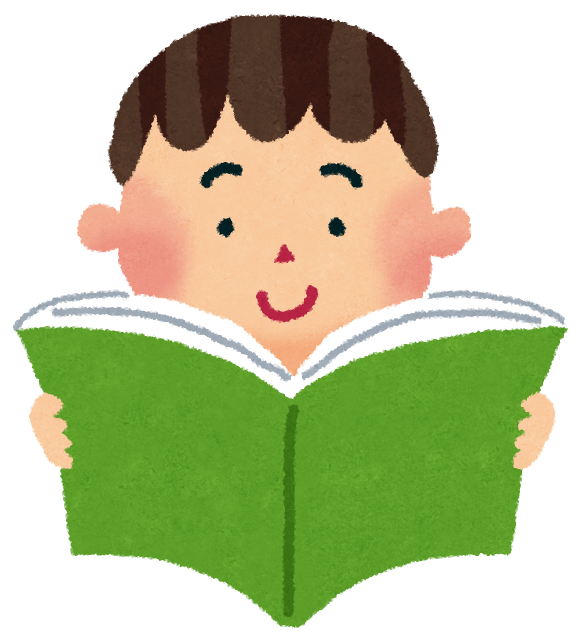
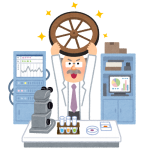

コメント